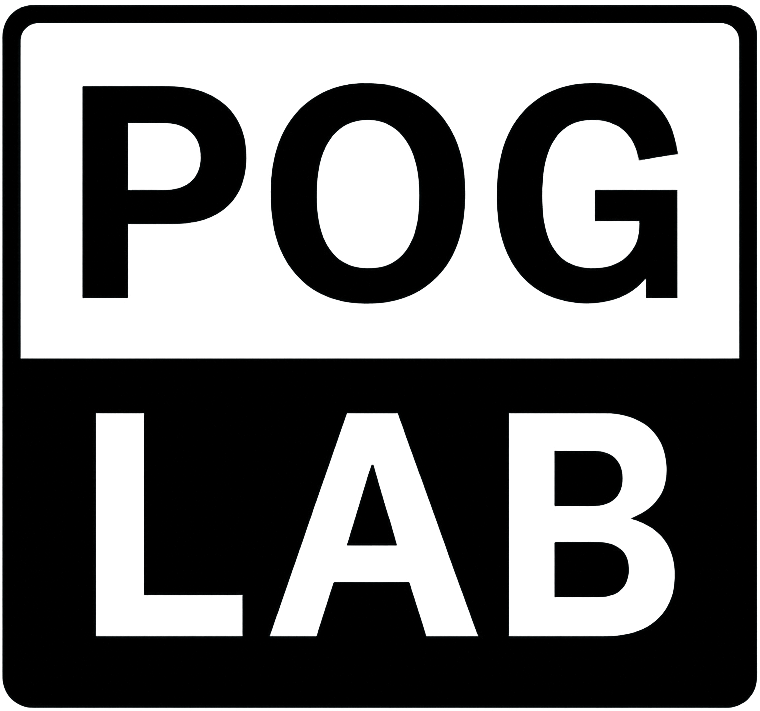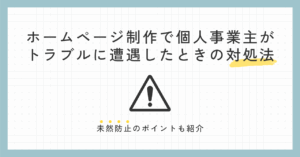ホームページ制作でトラブルにならないための”最低限の基礎知識”
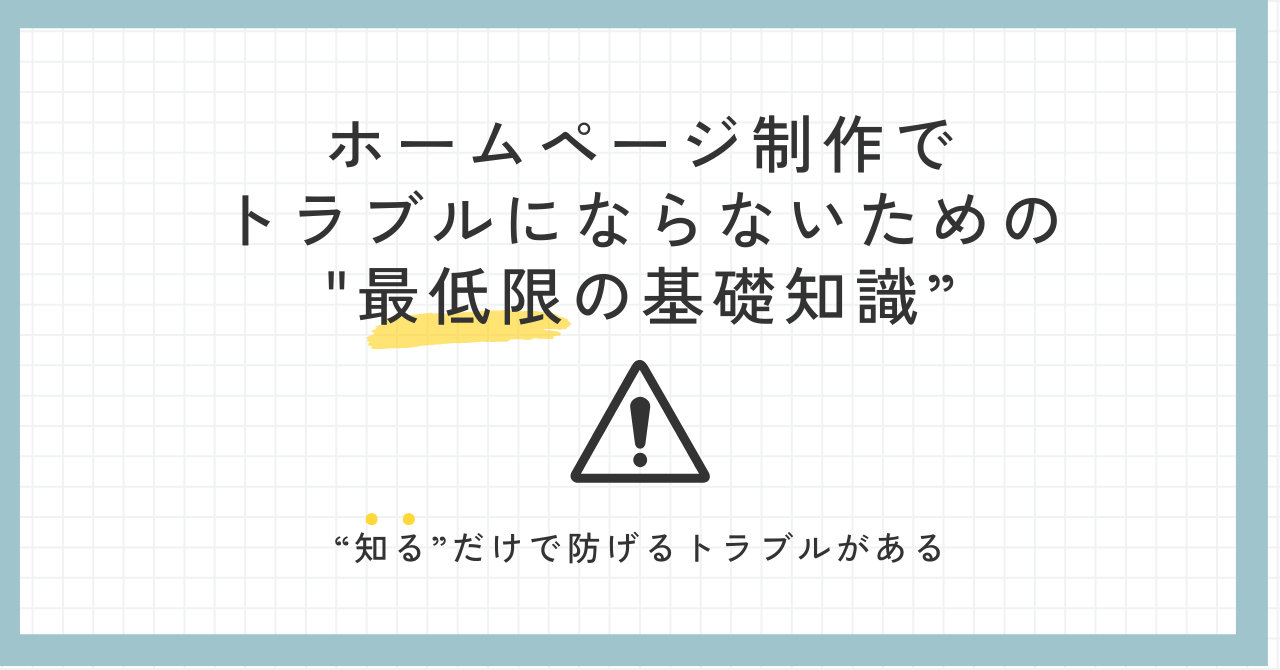
POG lab. Web Factory ディレクターのナカタです。
ホームページ制作は高額です。
にもかかわらず、専門用語が多く、Webの知識がないと必要以上の機能をつけられて費用がふくらんだり、契約内容をよく理解しないまま進んで後から「こんなはずじゃなかった」となるケースも少なくありません。
実際、「契約解除しようとしたら高額な違約金を請求された」「相手の言いなりで著作権を取られリニューアルできなかった」などの相談をよくいただきます。
“これだけは知っておいたほうがいい”という基本知識としての用語、それに関する注意点を解説します。
知識武装し、トラブルを回避しましょう!
基礎知識・用語表
| 用語 ※クリックで注意点解説 | 説明・なぜ重要? | 相場・目安 (2025) |
|---|---|---|
| ドメイン | あなたのサイトの住所のようなもの。例: “example.com”。唯一無二の文字列なので、取り扱い要注意。 | 年 1,000〜3,000 円 |
| サーバー | サイトのデータを置く土地のようなもの。 | 月 1,000〜8,000 円 |
| CMS | 手軽に更新できることを目的に開発されたツール。wordpressが有名。 カスタマイズ性=保守コストに直結 | 無料〜特殊な高性能CMSは高額 |
| SSL 証明書 | 鍵の役割。常時 HTTPS 化しないとSEO・信用に影響。 | 無料〜年 1 万円程度 |
| SEO | 検索に出るようにサイト内部を整える。表示速度やアクセシビリティ(快適性)など必要な施策が多い。 | 内部施策は追加費用なし。十分な施策を行なっていない事業者も多いので注意。 |
| レスポンシブ対応 | いわゆるスマホ表示。現代では必須要件。 | 追加費用なしが一般的 |
| 所有権条項 | デザイン/コード/写真の帰属。 明確化していないと運用会社を移行する際、トラブルの原因になりやすい。 | 契約書に必ず明記 |
ドメイン=インターネットの“住所”
- 例:
example.com、〇〇.co.jp - 年間コスト:一般的に1,000〜3,000円。高額プランを提示されたら要確認。(すでに取得された他者のドメインを買い取るという場合は高額になる可能性もあります)
建物の登記と同じで、自社名義にしておかないと引っ越し(移管)に高額な手数料を請求されることがあります。(相場:1.5万円~程度)
名義を預ける場合は、譲渡は可能か、その場合の費用を必ず確認しておきましょう。
サーバー=データを置く“土地”
ホームページのデータを格納する場所。
元々サーバーを持っている・契約している方を除き、制作会社がサーバーを管理します。
制作費と別見積もりの場合があるため、
制作費にサーバー費用が含まれているか否か、しっかり確認しましょう。
主に3種類あり、それぞれ予算・規模で使い分け、中小企業サイトでは「共有サーバー」を使用します。
| 種類 | 例え | 価格感 | 向いているサイト |
|---|---|---|---|
| 共用サーバー | 大型マンション | 月1,000〜2,000円 | 一般的なWEBサイト |
| VPS | 小さな一戸建て | 月3,000〜6,000円 | EC/中規模アクセス |
| クラウド | 好きなだけ拡張できる土地 | 従量課金 | 大規模・急成長サイト |
ドメイン同様、引っ越し(移管)に高額な手数料を請求されることがあります。(相場:5万円~30万円程度)
制作会社の「保守費用3万円/月」の内訳が“バックアップ1回+問い合わせ窓口”だけ…なんてことも。
内訳を確認しましょう。
CMS=コンテンツを入れる“家”
プログラミングができなくても手軽に更新できることを目的に開発されたツール。もっとも有名なのがWordPressです。
信頼性・流動性を加味して、予算さえ合えば圧倒的にWordPressをおすすめします。
| 種類 | 制作費の目安 | メリット・デメリット | 向いているサイト |
|---|---|---|---|
| WordPress | 20万円〜 | 自由度が高くて情報も多いが、セキュリティ管理の手間がある。 | 更新頻度が高い/SEO対策したいサイト |
| ノーコード (Wix・STUDIOなど) | 10万円〜 | 簡単に作れるが、機能や自由度が少ない。 | 低予算で小規模な情報発信をしたい場合 |
| 独自CMS | 50万円〜/月額費用あり | 業務にぴったり作れるが、高コスト&他社に移しにくい。 | 大企業・特殊な機能が必要な業界向け |
独自CMSは運用会社に手綱を握られてしまうので、特別な事情がない限りおすすめしません。
どのCMSを選んでも、「今後ほかの運用会社に移行しても更新できますか?」と必ず確認!
SSL証明書=“通信のカギ”
SSL証明を取ると、データが暗号化され盗み見防止に。ホームページを公開するには欠かせない施策です。
無料SSL(Let’s Encrypt)が主流。有料を勧められたら用途を確認。
SEO=“看板”
SEO(エスイーオー)は「検索エンジン最適化」のこと。
例えば、Googleで「東京都 グルメ」と調べたときに、自分のサイトが上のほうに出るように工夫すること。
検索結果の上位に表示されるようにすることをSEOと表現します。
一方、内部SEOとは、自分のホームページの中身(プログラム等)をわかりやすく整えることで、検索エンジンに「このページはいい内容だ」と思ってもらう工夫のことです。
SEO対策にはたくさんの要素があり、トレンドや検索アルゴリズムによって変わっていきます。そのため、継続的な運用が非常に重要です。
ただし、内部SEOは、サイトを作る制作会社の設計力や知識で決まる部分が大きく、「最初にきちんとやってあるかどうか」が今後に大きく影響します。
ところが、最低限の内部SEOすら行っていない制作会社も少なくありません。
最低限の内部SEOのチェックポイントを知っておくと安心です。
例えば:
- ページごとに適切なタイトル(titleタグ)と説明文(meta description)が設定されているか
- 見出しタグ(h1, h2など)でページの構造が整理されているか
- 画像にaltタグ(画像の説明)が入っているか
- スマホで見ても使いやすいデザインになっているか(レスポンシブ対応)
- 表示スピードが遅すぎないか
などが基本です。知識がないと難しいですよね。
Google Lighthouseなど、WEB上で簡単にチェックできるツールがありますので、検証は手軽に行えます。
契約前に「titleタグやaltタグは設定してもらえますか?」などと聞いてみましょう。
事例を公開していれば、そのサイトをチェックツールに入れて評価を見るのもおすすめです。
レスポンシブ対応=“スマホ対応”
PCだけでなく、スマホ表示で崩れないように対応することです。
現代では必須要件。今時、別料金はナンセンスです。
技術に差が出る部分でもあり、想定ユーザーがタブレットなどの場合はしっかり対応してもらえるか確認しましょう。
所有権条項
ホームページ制作で使われる「デザイン」「コード(HTML/CSSなど)」「写真やロゴ」などの著作物が誰のものになるかを決める契約項目のことです。
これが曖昧だと、サイトを別の会社に移そうとしたときに「デザインはうちの所有物なので使えません」と使用を制限されたり、追加費用を請求されることがあります。
よくあるトラブル例
- 納品後も「著作権は当社にあります」と言われ、修正に過剰なお金がかかる
- コードや画像の再利用を禁止され、リニューアル時にゼロから作り直しに
- 管理画面にアクセスできない/データの持ち出しを拒否される
契約前に「所有権は納品後すべてこちらに移りますか?」「移管時の制限はありますか?」と確認するだけで、防げるトラブルがたくさんあります。
まとめ——“知る”だけで防げるトラブルがある
ホームページ制作は一度契約すると長期間にわたって付き合うことになるため、
最初の段階での知識と確認がとても重要です。
専門用語をうやむやにされたまま契約を進めると、あとから思わぬ費用や制限に悩まされることも。
今回ご紹介した基本知識を持っているだけで、不利な条件やトラブルを回避できる確率がぐっと上がります。
重要なのは、
「契約前にしっかり確認すること」
「納品後、自社で管理・運用できるかを明確にしておくこと」
です。
ホームページは作って終わりではなく、「育てていく資産」です。
だからこそ、信頼できるパートナー選びと、最低限の知識武装が、未来の安心に繋がります。
POG lab. Web Factoryでは、知識がなくても安心して進められるよう、ひとつひとつ丁寧にご説明しながら制作を行っています。
「わからないことがわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
また、ホームページ制作のトラブルに遭った方の相談・会社移行のサポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事は2025年7月13日時点の情報をもとに執筆しています。法令や料金は最新版を確認してください。